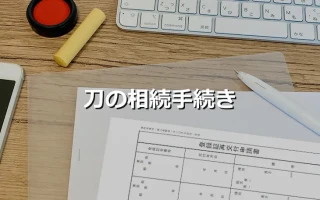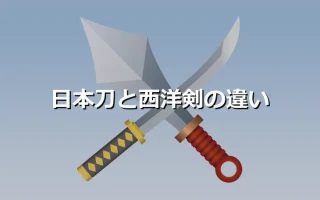脇差は、日本の伝統的な刀剣で、武士にとって欠かせない存在でした。
本記事では、脇差の種類や本差(日本刀)との違い、さらに注目の名刀などをご紹介します。
脇差とは
脇差(わきざし)は、日本の伝統的な刀剣の一種で、主に武士によって使用されました。通常、刃の長さは短刀よりもやや長く、刀剣よりも短いことが特徴です。
名前の由来は、帯に差して身につけることが一般的であったため、「脇に差す」から「脇差」と呼ばれるようになったというのが定説です。
脇差が広く普及した背景には、江戸時代初期に制定された「武家諸法度」が大きな影響を与えています。この法令は武士の身分や行動を規定し、特に「二本差し」と呼ばれる、脇差と本差(日本刀)を併せて身に着けることを推奨しました。
脇差はもともと、平安時代や鎌倉時代から防衛用の武器として携帯された伝統的な刀剣でしたが、江戸時代の武士にとって、脇差は単なる武器ではなく、身分や名誉を示す象徴としても重要な意味を持つようになります。
さらに、腰に刀をつけることが許されない町人や百姓も所持が認められていたため、江戸時代に脇差の需要は急増し、日本刀よりも多くの脇差が作られるようになりました。
刀の名工たちはこの時の流行に乗って、本差に匹敵する技術で、華麗な脇差を数多く残しています。一方、明治維新後には武士の身分制度が廃止されたため、脇差の制作は衰退していきました。
脇差と本差の違い
次に、江戸時代の武士が日常的に所持していた、脇差と本差(日本刀)の違いについてご説明します。
本差は通常、刃渡りが1尺8寸60cm以上と長く、主に戦闘用に適した設計がされています。そのため、戦場や武道での使用を意図した武器として、威力や斬撃に優れています。
一方、脇差は刃渡りが1尺未満~1尺9寸(約30〜60cm)と比較的短いため、携帯しやすく抜刀もしやすいというメリットがあります。戦闘時に脇差を利用する際は、相手との距離を詰めて素早く使用できるため、武士たちの護身用や戦術的に優れた武器とされました。
脇差の種類
脇差の刃の長さは3種類に分けられます。
- 大脇差:
刃渡りが1尺8寸(約54.5cm)から1尺9寸(約60.6cm)未満のものを指します。長さがほぼ60cmに近いため、戦闘や戦場での使用が主な目的となりました。戦闘時に攻撃力が高いため、戦場での武器として重宝されました。 - 中脇差:
刃渡りが1尺3寸(約40cm)から1尺8寸(約54.5cm)未満のものを指し、主に護身や近接戦闘に適したサイズです。日常的に携帯するのに便利で、軽量で取り回しが良いため、実用性が高かったとされます。 - 小脇差:
刃渡りが1尺3寸(約40cm)未満のものを指します。中脇差に続き護身や近接戦闘に適したものです。その小ささから隠し持つこともできたので、一般市民も携帯していました。
脇差は、それぞれのサイズによって目的が異なり、小脇差は日常使い、中脇差は日常使いと戦闘用、大脇差は戦場での武器の支援用と、用途に応じて使い分けられていました。
有名な脇差
脇差には、多くの名刀が存在し、戦国時代や江戸時代を通じて製作されました。特に優れた刀工によって作られた脇差は、美しい刃文や優れた技術が特徴です。
また、脇差には、重要文化財に指定されるほど高い評価を受けるものもあり、一部の作品は美術的・歴史的価値が認められ、刀剣愛好家や研究者の間で高額な取引が行われることもあります。
以下に、有名な脇差を2つご紹介します。
にっかり青江
作者:刀工一派「青江派」
制作年:平安時代末期から南北朝時代
特徴:刃長は約2尺弱(60.3cm)の大脇差で、備中国青江(現在の岡山県倉敷市)で栄えた刀工一派によって作刀されました。「『にっかり青江』は備中青江派の代表作で、鎌倉時代初期に作刀されたと考えられています。その伝承として、幽霊を斬った際の逸話があり、『にっかり』の号がつけられました。目釘孔が3個あり、金梨子地の四つ目結紋散糸巻の太刀拵が付いています。また、鞘には五三桐散と四つ結紋が金蒔絵で施されています。
鯰尾藤四郎
作者:粟田口吉光(あわたぐちよしみつ)
制作年:鎌倉時代末期
特徴:もともとは織田信長の次男・織田信勝が所有し、当初は1尺2寸9分(約39.1cm)の薙刀でした。豊臣秀吉の手に渡った後、「大坂夏の陣」で炎に包まれてしまいましが、徳川家康が焼き直しを命じて1尺2寸7分(38.5cm)の脇差によみがえりました。刃先部分の丸みが特徴的で、鯰尾(なまずお)に似た形状をしていることから、「鯰尾藤四郎」と呼ばれます。
脇差の鑑定方法と価値
脇差は、戦国時代から江戸時代にかけて、貴族や大名、武士の間で取引されました。特に名刀は高額で取引され、時には相続の際に重要な価値を持つこともありました。
この章では、脇差の鑑定にまつわる情報をご紹介します。
脇差の鑑定方法:専門的な視点から見極めるポイント
脇差の鑑定は、脇差の価値を判断するためには、以下のような鑑定基準が用いられます。名刀の場合、刀工の流派や作風によって価値が決まるため、熟練の鑑定士による評価が重要です。
- 刀身の形状と反り:
時代や刀工によって特徴的な形状があり、それが価値の指標になります。 - 刃文(はもん)の特徴:
刃の模様や焼き入れ技術による美しさや独自性が重要です。 - 地肌(じはだ)の質感:
鋼の鍛え肌や地鉄の状態は刀工の技量を示します。 - 銘(刀工の刻印):
刀身に刻まれた刀工の銘は、その製作者や流派を特定するための重要な情報源です。
これらの要素を総合的に評価し、専門の鑑定士が市場価値や歴史的価値を判断します。また、鑑定書の有無も信頼性を高める要因となります。
脇差の市場価値とは?
名刀である脇差は非常に高価であり、現在でも骨董品として取引されています。刀の状態や希少性、歴史的背景によって価格が大きく異なり、通常は1万から十数万円、高いものでは百万円を超えるものもあります。
まとめ
この記事では、脇差とはどういうものなのかを中心に解説しました。脇差は、単なる武具としての役割を超えて歴史や文化とともに流通し、日本刀工芸の技術の粋を伝える大切な骨董品のひとつです。
現在もなお、名刀とされる脇差の中には、重要文化財や重要刀剣として国の保護を受けているものが数多く存在し、日本の伝統文化を後世に伝える遺産としての役割を担っています。
脇差が流通した物語や背景を知ることで、さらに各作品について深く理解し、楽しむことができるでしょう。