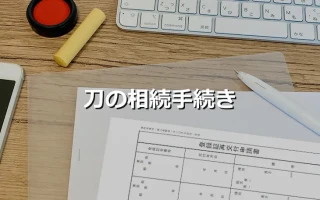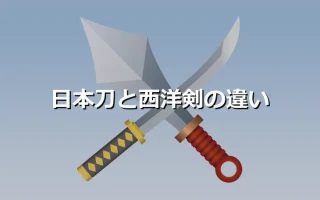日本刀は、日本の伝統的な刀剣類として、古くから独自の発展を遂げてきました。また、日本刀は国内だけでなく国外からの人気も高く、世界的にその価値が認められています。
そこで、今回は日本刀の歴史について、時代の変遷とともにご紹介いたします。日本刀の魅力を知ることで、あなたもきっとその魅力に引き込まれることでしょう。
日本刀の起源
日本刀の歴史は、古墳時代(約3世紀〜6世紀)にまでさかのぼります。鉄の加工技術や製鉄技術が朝鮮半島から伝来したことをきっかけに、日本でも刀剣類が制作されるようになりました。
この頃の日本刀は、「直刀」と呼ばれる、まっすぐで反りがないタイプのものが主流で、中国や朝鮮半島から伝わった製鉄技術の影響を受けているのが特徴です。また、用途も主に装飾品や儀式用として用いられることが多かったといわれています。
なお、この頃の刀は、日本刀ではなく「上古刀(じょうことう)」と呼ばれています。
日本刀の成立と時代の変遷
平安時代
平安時代(794年〜1185年)に入ると、武士階級が台頭し、戦闘で使用される刀の需要が高まりました。当時は騎乗での合戦が主流だったため、刀身が長く、馬上でも扱いやすいように反りが付いた刀が必要になったのです。その需要に伴い誕生したのが太刀(たち)という日本刀で、刃長はものにもよりますが、約80cm前後と直刀に比べてかなり長いものになりました。 この太刀の登場によって、現在の片刃の湾刀である日本刀が成立したのです。
なお、この時期から1595年(文禄4年)頃にかけて制作された刀は、「古刀(ことう)」と呼ばれています。
鎌倉時代
鎌倉時代(1185年〜1333年)は、日本刀の形状や製作技術に大きな変化をもたらした時代になります。武士階級が政権を握ったことで、実戦用としてより優れた日本刀が求められ、大きく発展を遂げました。この時代に作刀された日本刀は、「鎌倉刀」(かまくらとう)とも呼びます。
この頃の日本刀は、平安時代に確立された日本刀の美しい形を受け継ぎつつ、刀の鋭さ、耐久性、そして切れ味が以前のものより高くなったのが特徴です。
また、鎌倉時代末期になると、日本刀はより長く派手な見た目のものが好まれるようになりました。そのため、通常の太刀よりも約50~60cmほど長い大太刀と呼ばれる日本刀も登場するようになります。
室町時代
室町時代になると、大太刀のような長い刀は衰退していきました。
また、日本刀が大量生産されたことにより、下級の武士や農民などにも行き渡るようになります。そのため、合戦の形も、騎乗での合戦から徒歩での集団合戦のスタイルが主流となっていきました。それに伴い、打刀(うちがたな)と呼ばれる、刃長が約60cmで反りが浅く、扱いやすいタイプの日本刀が登場しました。
この打刀は、現代の私たちが日本刀として最もポピュラーに認識しているタイプの日本刀になります。
江戸時代前期~中期
戦国の世が終わり、江戸時代に入ると、平和な時代が続いたため、日本刀は戦闘用としての需要を失っていきます。そのため、この時代の日本刀は装飾が多く、華美なものが多く制作されました。 また、戦闘用の打刀の需要が減ったことに伴い、日常的にも帯刀できる、「脇差」や「短刀」など、用途や状況に応じてさまざまな刀が作られるようになったのもこの時代です。
なお、桃山時代末期から江戸時代中期頃にかけて制作された日本刀は、「新刀(しんとう)」と呼ばれています。
江戸時代後期
江戸時代後期のいわゆる幕末の頃になると、黒船の来航をきっかけに、攘夷運動(外国勢力を国内から追放する運動)が活発化し、国内の治安が悪化します。それに伴い、衰退していた日本刀の需要が再び高まり、盛んに制作されるようになりました。
この時代に制作された日本刀は、「新々刀(しんしんとう)」と呼ばれています。
明治時代
明治時代(1868年~1912年)に入ると、日本は近代化を進め、日本刀が実践で用いられることはほとんどなくなりました。また、「廃刀令」によって、軍人や警察などの一部の仕事についている人しか帯刀が許されなくなったため、日本刀の代わりに軍刀や儀礼刀などの刀が盛んに制作されるようになったのです。
廃刀令以降に制作された、数少ない日本刀は「現代刀」と呼ばれています。
昭和時代以降
昭和時代、太平洋戦争などをきっかけに、武器生産を目的として各家庭で保管されていた日本刀の多くは回収され、消失してしまいました。
しかし、戦後に文化財保護法が制定され、重要な文化財として指定された刀剣は、公共の利益を守ること目的として、保存が義務付けられています。特に、「重要文化財」に指定された刀剣は、修復や保護のための厳格な管理のもとで保管されています。
現代まで受け継がれてきた日本刀のその後
現在、歴史的価値が高いと認められている日本刀の多くは、地方自治体や美術館、博物館に所蔵されており、一般の方でも見に行くことができるようになっています。
以下に、有名な日本刀の所蔵機関と、所蔵している日本刀をご紹介いたします。
- 東京国立博物館(東京都)
所蔵している日本刀:相州貞宗、福岡一文字良房、三条宗近、大包平 - 刀剣博物館(東京都)
所蔵している日本刀:太刀 銘 国行(来)、太刀 銘 延吉 - 京都国立博物館(京都府)
所蔵している日本刀:銘 則国、陸奥守吉行、銘 山城国西陣住人埋忠明寿
まとめ
日本刀の起源は、古墳時代までさかのぼり、平安時代に日本刀として成立してからは、時代の変遷とともに進化・発展を遂げてきました。現代においても、日本の重要な財産として、各所蔵機関などで保管されています。
もし、本記事をご覧になって日本刀に興味を持たれた方がいらっしゃいましたら、ぜひ博物館などに足を運び、その刀が体現する歴史や、刀匠たちの技術に思いを馳せながら、ぜひじっくりと鑑賞してみてください。