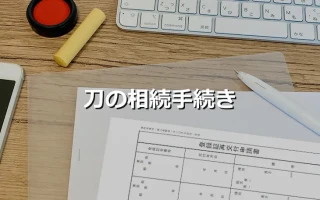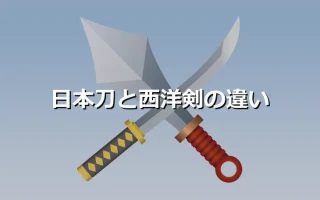日本刀と聞くと、多くの方は、「江戸時代の侍が腰に差しているもの」といったイメージが思い浮かぶのでは、と思います。もちろんそれも正解なのですが、実は日本刀にはもっと多くの種類があるということはご存じでしょうか。
この記事では、日本刀の種類とその特徴、日本刀の構造などについて幅広くご紹介します。この記事を通して、日本刀について興味のある方は、ぜひご参考にしてください。
日本刀の種類と特徴
日本刀の種類は大きく分けて7種類に分類されます。
それぞれの特徴や用途について、以下で詳しくご紹介いたします。
直刀
直刀は、日本刀の中でも非常に古い時代のものになります。
直刀の形状は、その名の通り、刀身がかなり直線的です。刀身に反りがある日本刀が多い中で、この直刀はかなり特徴的な見た目をしています。
直刀が作られたのは、主に古墳時代~平安時代中期以前と言われていますが、この時代の直刀のほとんどは出土品であるため、製作年代を明確に判別することはほぼ不可能です。
用途としては、戦闘用の他、儀式に使用されたり、献上品・贈答用として、主に当時の権力者たちから重宝されたという説が有力です。
太刀
太刀は、主に平安時代から室町時代ごろまでに制作されていた、大型の日本刀です。他の日本刀とは異なり、刃長が長く、反りが大きいことが最大の特徴です。 太刀は、主に太刀緒(たちお)と呼ばれる紐や皮が2本鞘に取り付けられており、腰から吊り下げて携帯されていました。
また、太刀は刃長の長さによって、3尺(約90cm)以上ある「大太刀」と、2尺(約60㎝)未満の「小太刀」に分けられます。
【大太刀】
大太刀、は主に当時の権力者や身分が高い物のみが所有していた貴重なものです。
用途としては、主に神社などへ奉納するために制作されていましたが、馬上からの攻撃をするための武器として戦場でも使用されていたといわれています。
【小太刀】
小太刀は、鎌倉時代ごろに制作されていました。刃長が短いことから、脇差と間違われがちですが、刀身の反りや形状が太刀と同様であるため、別物として分類されています。
小太刀がどのような場面で使用されていたのかは、よく分かっていません。
打刀
打刀は、日本刀の中でも最も代表的なもので、主に室町時代後期から江戸時代にかけて制作されました。一般的に日本刀というと、この打刀のことが差す場合が多いでしょう。
刃長は約60cm前後で、刀身の反りは比較的浅いのが特徴です。打刀は太刀と比べて刀身が短いため、素早く鞘から引き抜いて攻撃することが可能でした。
脇差
脇差は、打刀よりも短い日本刀で、主に打刀とセットで腰に差して携帯されていました。刃長の長さによって、1尺3寸(約40㎝)未満の「小脇差」、1尺3寸(約40㎝)から1尺8寸(約54.5㎝)未満の「中脇差」、1尺8寸(約54.5㎝)から2尺(約60.6㎝)未満の「大脇差」の3種類に分類されます。
脇差は打刀に比べて知名度は低いですが、実は実用的な日本刀として、一般的に広く使用されていた刀です。
時代劇などのイメージから、江戸時代に刀を帯刀できたのは武士だけ、と思われている方も多いですが、実際は農民なども道中の護身用として、道中差(どうちゅうざし)と呼ばれる脇差を帯刀することができました。
短刀
短刀は、刀身が脇差よりもさらに短く、一尺(約30cm)未満の小型の日本刀です。女性や子供でも扱いやすいものとして、主に護身用として使用されていました。
短刀は、所有者の身分や地位、財産などを示すために、豪華な装飾が施されたものが多いのも特徴です。
薙刀(なぎなた)
薙刀は、長い柄に反りが大きい刃をつけた日本刀で、主に平安時代に制作されていました。
間合いが広いため、歩兵・騎兵ともに使用できる武器として長く使用されていましたが、その長さゆえに味方も傷つけてしまうという欠点もありました。
槍
槍は、薙刀と同様に長い柄を持っていますが、先端についている刃は短いのが特徴です。時代によってその平均的な全長は異なりますが、およそ3~6m前後にもなるかなり大型の日本刀になります。
槍は、刃や柄の長さ、先端の刀の形状から、様々な種類に分類され、代表的なのは、素槍、片鎌槍、十文字槍などです。
日本刀の構造と各部位の名称
まず、日本刀は刀身(本体部分)と刀装(刀身を包んでいる外装部分)から構成されています。ここでは、それらの構造について、詳しくご紹介いたします。
刀身の構造
日本刀の本体部分である刀身は、主に9個のパーツから構成されています。
- 切先(きっさき):
刀身の先端部分。敵を斬ったり、刺したりする部位。 - 刃(は):
物を切ったりする部分全体のこと。 - 刃先(はさき):
刃の端の部分のこと。匂口(においぐち)ともいう。 - 物打(ものうち):
刀身部分のうち、最も強靭でよく切れる部分のこと。 - 峰(みね):
刃と反対の背中側の部分のこと。棟(むね)ともいう。
時代劇でもよく聞く「峰打ち」とは、この峰の部分で敵を打つ技法のこと。 - 鎬(しのぎ):
刀身の側面(刃と峰の間)にある、筋のこと。日本刀を「薄くて軽いが、耐久力が高く頑丈なもの」にするために重要な部分。
慣用句の「鎬(しのぎ)を削る」の語源にもなっています。 - 鎺(はばき):
刀身と鍔(つば)が接する部分にはめる金具のこと。鞘に納めた刀身が抜けないように固定する目的がある。 - 茎(なかご):
直接触る、持ち手の部分のこと。 - 目釘穴(めくぎあな):
目釘(めくぎ)を挿し、刀身を柄に固定するための穴。
刀装の構造
日本刀の外装部分である刀装は、主に以下の6個のパーツで構成されています。
- 柄(つか):
日本刀を使用する際、実際に手で握る部分。 - 柄頭(つかがしら):
柄の末端部分で、柄の角を補強する目的で装着されている金具のこと。 - 目釘(めくぎ):
刀身を柄に留めて固定するための留め具。 - 鞘(さや):
刀身を納めて保護するための、筒状のカバーのこと。 - 鯉口(こいくち):
鍔と接する、鞘の口部分のこと。 - 鍔(つば):
柄を握る際、手が刀身に滑っていかないように保護したり、刀全体の重心バランスをとるためにつける金具のこと。
まとめ
日本刀とは一口にいえど様々な種類があり、それぞれに特徴や用途、制作年代の違いがあります。日本刀の種類、また刀身や刀装の構造を知ることで、一層刀剣の魅力を味わうことができます。