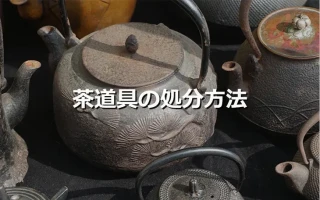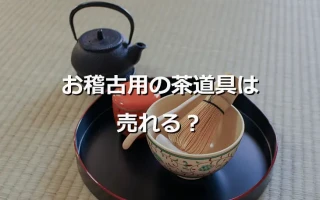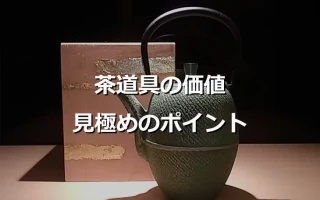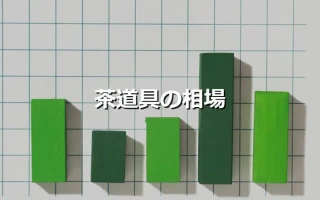茶道具の中で特に重要な役割を果たす棗(なつめ)をご存じですか?棗は、抹茶を保存し入れておくための道具であるだけでなく、茶道の魅力を引き立ててくれる存在でもあります。本記事では、棗の種類や選び方のポイントについて詳しく解説します。
茶道具 棗とは
棗(なつめ)とは、茶道具の一つで、抹茶を保存し、供するために使用される容器です。ころりとした愛らしい形が果実の「なつめ」に似ているという理由でそう呼ばれるようになりました。そんな棗の持つ深い歴史や役割、装飾の美しさを知り、棗の世界に足を踏み入れてみましょう。
棗の歴史と起源
棗の歴史は、茶道の発展と深く関連しています。その起源を辿ると、茶の文化が生まれた中国にまで遡ることができます。中国では古くから抹茶を使用する茶の儀式が行われ、専用の容器として棗が用いられていました。日本に茶の文化が伝わる過程で、棗も独自の進化を遂げ、やがて日本独自の形態と機能を持つようになりました。
日本において、茶道は武士や貴族の間で広まり、その重要性が増していきました。特に、茶道の大成者である千利休が確立した「わび茶」の影響を受け、棗の形状やデザインは一層洗練され、茶道の美学を象徴する品物になりました。
利休の時代には、質素でありながらも深い美しさを持つ棗が求められるようになり、それが今日の棗の多様なデザインに繋がっています。現在では、棗はその材質や形状、装飾に至るまでさまざまなバリエーションがあり、棗のコレクター間でも根強い人気があります。
棗の本来の役割と使い方
棗の主な役割は、抹茶の保存です。抹茶は湿気や光に敏感で、保存状態が悪いと風味が失われやすくなります。棗はその特性を踏まえて設計されており、抹茶を最適な状態で保ってくれます。特に、木製や漆器製の密閉性の高い棗は湿気の侵入を防ぎ、抹茶の風味を維持するのに適しています。
使用方法としては、抹茶を棗に入れた後、蓋をしっかり閉じて外気や湿気を遮断します。取り出しには、専用の茶杓(ちゃしゃく:抹茶をすくう細長いさじ)を使うことで、無駄なく抹茶を扱い、風味を保ちながら抹茶を楽しめます。
棗の形状による種類
棗はその形状によっていくつかの種類に分かれ、それぞれに特徴があります。代表的なものとして、以下の3種類が挙げられます。
中棗(ちゅうなつめ)
茶道具全体の中でも人気が高いのが中棗です。中棗は丸みを帯びた形状が一般的で、手にしっかりと馴染む感覚が魅力です。
通常、約50グラムから100グラムの抹茶を収納できるため、日常的な使用はもちろん、稽古にも適しています。
また、濃い色合いの漆塗りや美しい装飾が施されることが多く、コレクターに人気の茶道具とも言えます。
小棗(しょうなつめ)
小棗は、茶道具の中でも特に可愛らしいサイズです。通常の棗よりも一回り小さく、持ち運びに便利な小棗は、涼しい季節に屋外で行われる野点(のだて)で活躍します。
小棗もデザイン性の高いものが多く、漆塗りや模様の入った作品など、好みに合わせて選ぶ楽しさがあります。
平棗(ひらなつめ)
平棗は、その名の通り平らな形状を持つ棗で、通常は大きめに設計されています。平棗は、広い口から抹茶をスムーズに取り出すことができ、稽古や茶会のシーンで使われることが多いため、目にする機会の多い種類と言えます。
棗の塗りと装飾による種類
次に、棗を特徴づける装飾や材質について、代表的なものをいくつかご紹介します。
金蒔絵・銀蒔絵
棗の装飾の中でも、金蒔絵と銀蒔絵は特にその美しさで知られています。いずれも、金や銀の粉を漆で膠着させることで、非常に高級感のある一品に仕上がります。
金蒔絵は、豪華で華やかな印象を与える金粉を使用します。金色は古来より高貴さや祝祭の象徴として重んじられてきたため、金蒔絵の棗は、特に格式の高いコレクションにおいて価値が高いとされています。
一方、銀蒔絵は、金に比べて柔らかな光沢感を持ち、洗練された印象を与えます。銀色は、落ち着いた品格を感じさせるため、日常的なコレクションやカジュアルな場面にも適しており、様々なシーンでその魅力を発揮します。
檜の棗
檜も棗に多く使用される素材です。檜は非常に高価で美しい木材として、伝統的な工芸品に多く使用されています。特に日本の茶道具、家具、仏具などに用いられることが多く、その独特な風合いと美しい木目が特徴です。檜は香り高く腐敗しにくいため、長年その価値を保つことができるのです。
漆塗り
漆塗りは、棗をはじめとする工芸品の選定では非常に重要な要素です。漆は自然素材であり、その美しい外観だけでなく、耐久性や防水性にも優れています。漆塗りの、手から伝わってくる違いを感じることも、棗の楽しみ方のひとつです。
また、有名な漆器産地で作られた棗は特に高い評価を受けています。以下に、代表的な漆器の産地とその特徴をまとめました。
- 輪島塗(石川県): 輪島塗は石川県を代表する伝統工芸品の一つです。輪島市で採れる良質な土を下地に使用することで、漆器の強度を高めています。また、その美しい外観も輪島塗ならではの魅力です。
- 津軽塗(青森県): 津軽塗の特徴は、「研ぎ出し代わり塗り」と呼ばれる独特の技法にあります。この技法では、塗っては研ぐという作業を繰り返し、約40もの工程と2か月以上の時間をかけて仕上げられます。その結果、生まれる個性的な模様は他の漆器には見られない唯一無二のデザインとして高い人気を誇っています。
- 会津塗(福島県): 福島県会津地方で作られる漆器で、独特の魅力を持っています。松竹梅と破魔矢を組み合わせた模様は『会津絵』と呼ばれ、他の漆器と比べて溝を浅く、繊細に彫るのが特徴です。この手法により、装飾に柔らかさと温かみが感じられる仕上がりとなり、多くの人々に愛されています。
- 根来塗(和歌山県): 和歌山県岩出市の根来寺で誕生した根来塗は、その歴史と独特の美しさで知られています。もともとは僧侶が自分たちで使用するお盆や膳などを手作りしていたのが始まりです。根来塗の魅力は、使用を重ねることで朱色の下から黒色が徐々に現れ、深みと味わいが増す独特な色合いにあります。この変化が楽しめることから、現代でも根強い人気を誇っています。
選び方のポイント
棗は単なる道具としての機能を超え、歴史や職人技が反映された芸術品といえます。あなたのコレクションに加える際には、材質や状態を見て、じっくりと選びましょう。
Point1.材質
木製の棗…温かみのある質感と手に馴染みやすい特徴があり、長年使用することで独特の風合いが増します。特に希少な木材や特定の樹種を使用した棗は、コレクターズアイテムになりえます。
陶器製の棗…焼き物の特性を活かした質感や釉薬の美しさが楽しめ、視覚的な魅力も大きいです。また、陶器製は時代や流派によって特色が異なるため、特定の時代背景や作風は魅力的な選択肢となります。
Point2.塗装の状態
漆塗りの棗…艶やかな光沢と格別の手触りがある漆塗りは、塗りが均一であることや、艶感がしっかりと出ているかを確認しましょう。特に金蒔絵や銀蒔絵の装飾が施された棗は、職人の技術が光る部分であり、その仕上がりの精緻さに注目してください。金粉や銀粉の配置、艶感が適切であるかどうか、そして塗りの厚みや均一さが棗の価値を大きく左右します。
Point3.装飾技法
細かな彫刻や手描きの絵柄が施された棗は、その装飾に込められた職人の技術や芸術性が感じられ、コレクションに加える価値が一層増します。特に稀少なデザインや、特定の流派に基づいた模様や絵柄が施されたものは、歴史的な価値を持つ場合もありえます。
Point4.全体の状態を確認
棗の素材には象牙や陶器を使用した珍しいものもありますが、主流は木地や竹を使用したものです。ただし、木製の棗は湿気に弱いため、保存場所や状態が悪いとひび割れが生じ、さらに悪化すると裂けることもあります。購入の際には、まず全体を注意深く観察し、劣化やダメージがないかを確認することが大切です。
Point5.蓋裏の書付を確認
家元が書付を行った共箱付きの棗には、通常、上蓋の裏面に家元の花押が記されています。また、家元によっては、共箱の上半分に花押の一部を記し、蓋の裏側に残りの部分を記載するケースもあります。これらを確認することで、共箱と棗本体が正確に一致しているかを判断できます。
さらに、作家作品に家元の書付が添えられている場合、その希少性や価値が高まります。コレクターとして棗の収集をこれからお考えの方は、有識者の方へ見てもらったり、積極的に骨董市などで作品についての理解を深めることをおすすめします。
棗の価格帯と価値
棗の価格帯は、その材質や作り、装飾技法によって大きく異なります。
シンプルな木製棗は比較的手頃な価格で、数千円から数万円の範囲で手に入れることができます。しかし、陶器製や特殊な高級素材を使用した棗は、数万円から十万円以上に達することもあります。特に、職人の手による精緻な装飾や、希少性の高い素材を使用したものは、コレクターにとって貴重な作品となります。
ただし、高価なものが必ずしも自分にとって最適な棗であるとは限りません。棗を選ぶ際には、材質、装飾、職人技を考慮し、作品の独自性や歴史的価値を重視することも楽しみのひとつです。
おすすめの棗作家のご紹介
棗は、茶道における重要な道具のひとつとして、茶人たちに愛され続けてきました。その美しい漆塗りや精緻な装飾、そして長い年月をかけて熟成される風合いは、作り手の技術と心が込められた証です。
ここでは、歴史的に評価が高く、現在でも高額で取引されることが多い棗作家たちをご紹介します。
中村宗哲(なかむら そうてつ)
千家十職の塗師です。特に棗をはじめとする茶道具の制作において、その精緻な技術と美しいデザインで高く評価されています。彼の棗は、繊細な漆の塗りや独特の装飾が特徴で、使い込むほどに深みを増す色合いが魅力です。
清瀬一光(きよせ いっこう)
明治時代から昭和初期にかけて活躍した漆器の名工です。軽やかさと深みを兼ね備えており、その独特の風合いは他の作家の作品とは一線を画しています。精緻でありながらも品のある美しさを誇り、洗練されたデザインと巧みな技術で高く評価されています。
前端雅峯(まえはた がほう)
漆器の名工です。漆の塗りの美しさや繊細な装飾技法に特徴があり、漆器としての実用性と芸術性を兼ね備えた作品が多くあります。精緻な蒔絵や象嵌(ぞうかん)技法が施され、非常に高い評価を受けています。特に、自然を題材にした模様や花鳥風月を描いたデザインは、茶道具としての美しさを際立たせ、使用者に深い感動を与えるものです。
黒田辰秋(くろだ たつあき)
漆芸の名工として知られ、朱漆を使用した棗でも高い評価を得ています。彼の作品は、伝統的な技法と現代的なデザインを融合させたものが多く、精緻な漆塗りの表現が特徴です。
一后一兆(いちご いっちょう)
石川県出身の蒔絵師であり、輪島塗の名手としても知られています。豪華絢爛な作風が特徴で、大胆な色彩と構図ながら細部まで緻密に作りこまれた技術力が高く評価されています。特に茶道具の分野で名高く、棗などの作品は愛好家の間で人気となっています。
川端近左(かわばた きんさ)
200年以上の歴史を持つ漆工芸師です。現在の六代目は1947年生まれで、2000年に襲名しました。茶道具、特に蒔絵を施した棗や盆、重箱などを得意とし、三千家からも高く評価されています。中でも豪勢な蒔絵のあしらわれた棗は一見の価値があります。
このように、棗作家たちはそれぞれの時代背景や技術、個性を反映した作品を生み出し、今もなお愛され続けています。ご紹介した作家はほんの一部ですが、彼らの手による棗は、芸術品としての価値が認められ、時には驚くような高値がつくこともあります。
棗の保管方法やお手入れの注意点
棗は、繊細な茶器であり、適切な保管が欠かせません。保管方法の注意点を3つご紹介します。
保管する前に確認を
保管前には必ず棗の表面をチェックし、抹茶や汚れが残っていないか確認してください。これらが残ったままだと、カビや嫌な臭いの原因になります。また、棗は漆塗りが多いことで知られていますが、漆は紫外線にも弱いため、直射日光が当たる場所や湿気が多い場所での保管は避けてください。
保管場所
保管する場合、湿気が少なく風通しの良い場所にしましょう。棗は湿気を吸いやすいため、湿度の高い環境ではカビが発生しやすくなります。そのため、木箱などの湿気を防ぐ容器に収納すると効果的です。さらに、乾燥剤を一緒に入れておくのも効果的です。
適切な保存環境が整っていない場合、自然とひび割れが進行することもあります。特に、保存場所が湿気の多い場所や温度変化の激しい場所だと、劣化が早く進むことがありますので気を付けましょう。
お手入れ方法
汚れを落とす際には注意が必要です。洗剤を使って無理に汚れを落とすと、素地や蒔絵が剥がれてしまったり、洗剤の臭いが残ることがあります。これが逆効果になることもあるため、洗剤の使用は避けましょう。
お手入れには、乾いた布で優しく拭くことをおすすめします。力を入れすぎず、優しく表面を拭くだけで十分です。
まとめ
茶道の道具として欠かせない棗は、形状や素材、装飾が多種多様であり、選ぶ際にはどの要素に重きを置くかが重要です。棗の選び方のポイントを押さえて、漆塗りや金蒔絵、檜の棗など、それぞれの装飾や質感を知りながら、コレクションしていきましょう。
古い棗を集める際には、ご自身のお好みや目的に合った棗の選定を行うことをおすすめします。まずはどんな作品があるのか、歴史的背景や作り手の技術にロマンを感じながら、骨董市や骨董品店へ足を運んでみましょう!