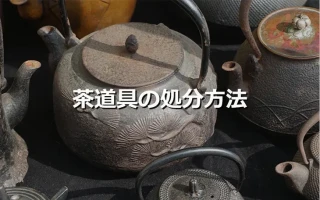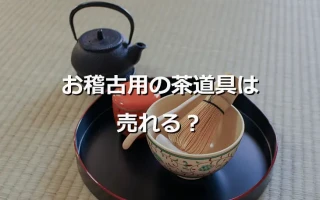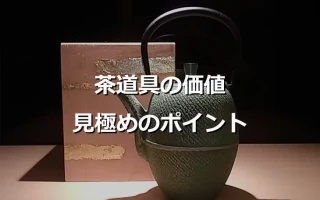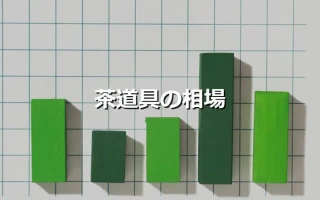茶道というと、多くの方は抹茶(濃茶)を点てるものというイメージを持つかもしれません。しかし、実は茶道には、抹茶を点てる「抹茶道」と、煎茶や玉露などの茶葉を淹れる「煎茶道」という2つの種類があります。この抹茶道と煎茶道では使用する道具も異なり、煎茶道において使われる道具は「煎茶道具」と呼ばれています。この記事では、煎茶道の基礎知識と煎茶道具の名前、それぞれの役割について詳しく解説していきます。
煎茶道の歴史
日本において煎茶道が始まったのは、江戸時代のこととされています。江戸時代初期に黄檗宗(おうばくしゅう)の高遊外(こうゆうがい)という僧侶が、長崎で煎茶の知識を習得し、その後京の都で煎茶を売り始めたことから、煎茶が広まったのです。
江戸時代中期になると煎茶の消費が増え、それに伴い煎茶道としての独自の道具や作法も発展していきました。抹茶道が織田信長や豊臣秀吉など、大名や権力者たちに親しまれた一方で、煎茶道は特に庶民の間で広がっていったのが特徴です。
煎茶道具の名称と役割
煎茶道具には、さまざまな種類があり、それぞれに役割があります。ここでは、各道具の名前と読み方、主な役割についてご紹介します。
烏府(うふ)
烏府(うふ)は、炭を入れておくための道具を指します。直径20cm位までのあまり大きくない物のことで、竹や籐で作られたものが多いのが特徴です。
煎茶道具の名称と役割(か行)
火斗(かと)
火斗(かと)は、火種を運ぶための道具で、一般的には十能(じゅうのう)のことを指します。火を扱うための道具であり、素焼きでシンプルな見た目をしている点が特徴ですね。
急須(きゅうす)
急須(きゅうす)は、茶葉を入れてお湯を注ぎ、茶を抽出するために使う道具です。急須の形状や材質は、茶の味に影響を与えるため、煎茶道では急須の選び方や使用方法が非常に重要とされています。
急須にはさまざまな種類があり、持ち手の位置で横手形、上手型、後手型、宝瓶の4種類に分けられ、それぞれに適した茶の種類が異なります。
また、急須内部にある「網」の構造にも種類があり、代表的なものとして帯網(おびあみ)、ポイポイ網、陶網(とうあみ)、平網(ひらあみ)、底網などが挙げられます。
急須台(きゅうすだい)
急須台(きゅうすだい)は、急須を置くための台です。木材や竹、金属や錫などさまざまな材質で作られており、形状も楕円形や正方形、葉っぱの形をしたものなど多岐にわたります。
建水(けんすい)
建水(けんすい)は、煎茶椀を洗ったり、器を温めた後のお湯や茶殻を捨てるための器です。「茶こぼし」とも呼ばれています。陶磁器や銅、漆器などの素材で作られており、使用目的に合わせて選ばれますね。
香合(こうごう)
香合(こうごう)は、茶室で焚くためのお香を入れる器のことです。煎茶道において、お香は茶室の雰囲気を整える重要な役割を果たします。
香合には装飾的な役割もあり、デザインや材質、形状が美術品としても高い価値を持つのが魅力でしょう。
煎茶道具の名称と役割(さ行)
茶具褥(さぐじょく)
茶具褥(さぐじょく)は、煎茶道具を置いておくために使われる敷物のことです。煎茶道具には割れ物が多いため、傷がつかないよう保護する役割も兼ねていますね。
水注(すいちゅう)
水注(すいちゅう)は、煎茶を淹れるために必要な水を入れておく器を指します。形や素材にはさまざまなものがあり、用途や好みに合わせて選べます。
煎茶椀(せんちゃわん)
煎茶椀(せんちゃわん)は、煎茶を注ぐための器です。一般的な湯飲みに比べると非常に小さなサイズで、可愛らしい印象を与えます。その理由として、古くはお茶が高価であったため、少量を楽しむ習慣があったからと言われています。
洗瓶(せんびん)
洗瓶(せんびん)は、煎茶椀を洗う際に使用する水を溜めておく器です。使用する水は飲用ではなく、器を洗い清めるために使われるものですね。
洗瓶を用いる際は、建水(けんすい)の上で水を使って器を洗います。
煎茶道具の名称と役割(た行)
棚(たな)
棚(たな)は、煎茶道具を置くために使われる道具です。主に2段の棚や3段の棚が用いられ、それぞれ「四方棚(しほうだな)」「松風棚(しょうふうだな)」など、異なる呼び名が付けられています。用途や美観に応じて選ばれることが多いですね。
茶心壺(ちゃしんこ)
茶心壺(ちゃしんこ)は、茶葉を保存するための器です。茶道では一般的に「茶入(ちゃいれ)」とも呼ばれます。この道具は茶葉の酸化を防ぎ、香りや風味を保つために欠かせないものとされています。
茶托(ちゃたく)
茶托(ちゃたく)は、煎茶椀を置くための受け皿です。熱い茶碗を直接手に取らせない配慮や、こぼれたお茶が衣服を汚さないための工夫として使われています。その形や材質は非常に多様で、流派によっても違いがあるのが面白いですね。
茶旗(ちゃばた)
茶旗(ちゃばた)は、茶会が行われていることを知らせるために掲げられる小さな旗です。茶席付近の樹木や特定の場所に取り付けることで、茶会の開催を示す目印となります。
茶量(ちゃりょう)
茶量(ちゃりょう)は、茶入れから茶葉をすくい取るための匙のことです。流派によって「茶合」「仙媒(せんばい)」「茶則」と呼び方が変わることもあります。竹製が一般的で、高価なものには彫刻が施されていることもあり、美術品としての価値も感じられます。
衝立(ついたて)
衝立(ついたて)は、炉屏(ろびょう)と同様に茗座(めいざ)の向こう側に立てることで、茶席の空間を区切る役割を果たします。一般的には屏風のような形状で、複数の板や布が連結したデザインが多いです。
提籃(ていらん)
提籃(ていらん)は、茶道具を収納して持ち運ぶための籠です。茶籠(ちゃかご)や器局(ききょく)と似た役割を持ちますが、屋外で使用されることが多いのが特徴です。
煎茶道具の名称と役割(は行)
羽箒(はぼうき)
羽箒(はぼうき)は、涼炉(りょうろ)についた灰を取り除き、清めるために使用される道具です。主に野雁の羽で作られていますが、鶴や鷹の羽を使用したものもあり、茶道具としての美しさも備えていますね。
花屏風(はなびょうぶ)
花屏風(はなびょうぶ)は、茶席を飾るために用いられる道具です。木や竹を柵のように組み、生花を飾って茶席の雰囲気を華やかに演出します。
柄杓(ひしゃく)
柄杓(ひしゃく)は、水やお湯を汲み注ぐために使用される道具です。煎茶道では、湯加減の調整が重要であるため、柄杓はその役割を担う欠かせない存在ですね。
火箸(ひばし)
火箸(ひばし)は、炭や香を挟むための箸状の道具です。炉用と風炉用の2種類があり、それぞれ用途に応じて使い分けられています。
瓶床(びんしょう)
瓶床(びんしょう)は、茶器を上に乗せるための台で、瓶敷とも呼ばれます。竹や藤の蔓で編まれたものが一般的で、茶具褥を傷めないよう工夫された作りが特徴です。
袱紗(ふくさ)
袱紗(ふくさ)は、煎茶道具を拭き清めるために用いられる布です。抹茶道では絹製が主流ですが、煎茶道では木綿製のものが使用されることも多いですね。
ボーフラ(ぼーふら)
ボーフラ(ぼーふら)は、湯を注ぐために使用される道具です。急須に似た形状をしていますが、素焼きで白い陶土を固めたシンプルな見た目が特徴で、その名前の由来はポルトガル語の「botija(壺)」から来ていると言われています。
煎茶道具の名称と役割(ら行)
涼炉(りょうろ)
涼炉(りょうろ)は、夏の茶会で使用される炉のことです。お湯を温めるための道具で、中に炭を入れて火をつけます。陶土を素焼きにしたものが多く、直接火に触れる仕様になっていますね。涼炉は煎茶道具の中でも特に大きな道具の一つです。
炉扇(ろせん)
炉扇(ろせん)は、炉を扇いで火力を調整するための道具です。見た目はうちわに似ており、竹と木の板で作られていることが多いです。火加減を細かく調整する際に役立ちます。
炉屏(ろびょう)
炉屏(ろびょう)は、茗座の向こうに立てて使用する屏風のことです。茶を点てる人と客座との境目を分ける役割を持ち、茶席全体の空間を整えるために欠かせない道具ですね。
まとめ
茶道は、大きく分けて抹茶道と煎茶道の2種類に分類されます。煎茶道の起源は江戸時代にさかのぼり、高遊外(こうゆうがい)という僧侶が煎茶を普及させたことがきっかけとなりました。抹茶道が主に大名や権力者に支持された一方、煎茶道は庶民の間で広がっていったのが特徴です。
抹茶道と煎茶道では使用される道具やその役割も異なり、それぞれが独自の文化を発展させてきました。煎茶道具には、歴史や文化が息づいており、一つ一つの道具に深い意味や役割が込められています。これを機に、煎茶道の魅力をぜひ感じてみてはいかがでしょうか。
また、中国で煎茶が流行っており、相場が高くなっています。自宅に眠っている煎茶道具を見直すきっかけになると幸いです。