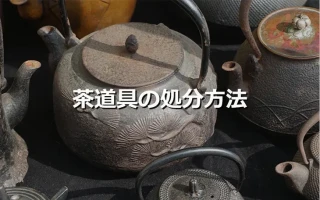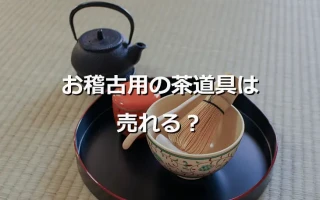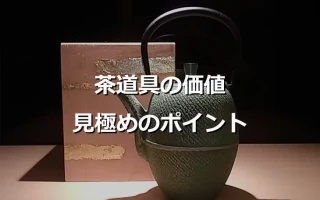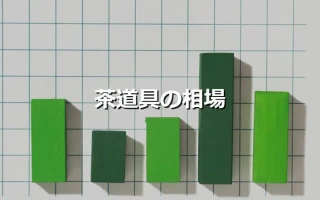茶道は古くから存在する日本の伝統文化の一つであり、茶道における作法や言葉は、その背後にある精神や哲学を反映しています。
本記事では、茶道の基本的な作法や、よく使用される言葉の意味について詳しく解説いたします。
茶道の基本作法
茶道における作法は、心を整え、他者を思いやるために大切なこととされています。作法の細かな部分は各流派によっても異なりますが、ここでは流派に限らず基本的なマナーとしての作法について、解説いたします。
席入りの方法
席入りとは、茶事や茶会に招かれたときに、茶席に入ることをいいます。
席入りをするときは、まず事前に手水鉢で手を洗い清めます。その後、茶室の入口で亭主(茶事や茶会の中心となる人)へ向けて「失礼します」と声をかけ、軽く一礼してから入室しましょう。
席へ向かう際には周りの席の人の迷惑にならないよう、静かに、足元に気を付けながら進みましょう。
ちなみにお茶の席で亭主に最も近い席に座る人のことを「正客(しょうきゃく)」、最も遠い席に座る人のことを「末客(まっきゃく)」と呼びます。
挨拶の仕方
出席者が着席すると亭主が挨拶をしますが、他の出席者の前に正客が代表で挨拶をします。
亭主がこちらを向いてお辞儀をしたら、他の出席者も一緒に頭を下げます。
お菓子の食べ方
挨拶が終わると、まずはお菓子が振舞われます。
お菓子を運んできてくれた人がお辞儀をしたら、感謝の意を込めてお辞儀を返します。
食べる際は、亭主から「どうぞお菓子をお取りください。」と声をかけられてから手を伸ばすようにしましょう。
お茶の飲み方
お菓子を食べ終わるくらいのタイミングで、最後にお茶が運ばれてきます。
目の前にお茶が運ばれてきたら、お菓子と同様に運んできてくれた人にお辞儀をします。その時、自分の次の席の人にまだお茶が運ばれてきていなかったら、「お先に頂戴します。」と一声をかけ、その人にもお辞儀をします。
その後、「お点前頂戴します。」と言ってもう一度頭を下げ、茶碗を両手で軽く持ち上げます。
飲む際は、茶碗を手の上で少し回してから飲むようにしましょう。お茶は一気に飲むのではなく、ゆっくりと味わって飲むのがマナーとされています。
飲み終えた後、茶碗の飲み口を指で軽く拭き、茶碗の正面(絵柄がある茶碗なら絵柄がある方が正面)を向こう側へ向けておきます。
茶道で使われる言葉一覧
茶道では、普段は馴染みのないような言葉が多く使われています。使い方や読み方などは流派によって若干異なる部分もありますが、一般的に使われている言葉は以下のとおりです。
| 用語(読み仮名) | 用語の意味 |
|---|---|
| 一期一会 (いちごいちえ) | 茶会での出会いは、一生に一度の出会いとして主客ともに誠意を尽くすこと |
| 一服 (いっぷく) | 点てられた茶を飲むこと |
| 居前 (いまえ) | 亭主が茶を点てる際に座る場所 |
| 薄茶 (うすちゃ) | 薄めの濃度で点てられた抹茶 |
| 大寄席 (おおよせ) | 大人数で開かれる茶会 |
| 主菓子 (おもがし) | 餡で作られた、羊かんや練り切りなどの生菓子 |
| 懐石 (かいせき) | 茶事において客に振舞われる料理 |
| 釜 (かま) | 湯を沸かすために使用する茶道具 |
| 通い畳 (かよいだたみ) | 亭主が茶道口から茶室へ入り、客人が座っている座席まで向かうまでの畳 |
| 貴人畳 (きにんだだみ) | 床の前の畳 |
| 切止 (きりどめ) | 茶杓などの柄の先端部分のこと |
| 客畳 (きゃくだたみ) | 客人の座席 |
| 客付 (きゃくつき) | 手前をする際に、亭主の座席から見て客人に近い方のこと |
| 濃茶 (こいちゃ) | 通常の2~3倍の濃度で立てられた抹茶 |
| 茶道口 (さどうぐち) | 亭主が使用する出入り口 |
| 捌く (さばく) | 帛紗や古帛紗を折り畳み、道具を清めること |
| 三千家 (さんせんけ) | 表千家、裏千家、武者小路千家の総称 |
| 膝行 (しっこう) | 立たずに膝のみで前進すること |
| 自服する (じふくする) | 亭主自身が自分で点てた茶を飲むこと |
| 正客 (しょうきゃく) | 最も亭主に近い席に座っている客人 |
| 相伴する (しょうばんする) | 正客の伴として、一緒にもてなしを受けること |
| 真・行・草 (しん・ぎょう・そう) | 所作や茶道具の格式などを表す言葉 |
| すい切り | 茶を飲み切る時に音を立てること |
| 席入り (せきいり) | 茶会や茶事に招待された際、茶室に入ること |
| 建付 (たてつけ) | 襖を閉めた時に当たる柱 |
| 茶入 (ちゃいれ) | 濃茶を立てるための抹茶を入れておく容器 |
| 茶事 (ちゃじ) | 茶道における正式なおもてなしとして開かれる茶会 |
| 茶筅通し (ちゃせんとおし) | 茶を点てる際や片付ける際に、茶筅の先端を調べること |
| 茶掃箱 (ちゃはきばこ) | 茶入や棗など、抹茶の粉末を入れておくための茶道具一式を収納する箱 |
| 亭主 (ていしゅ) | 茶会や茶事を主催する人 |
| 点前 (てまえ) | 客人の前で茶を点てる一連の作法と流れ |
| 点前座 (てまえざ) | 亭主の座席 |
| 床 (とこ) | 掛軸や花入、香合などを飾っておく床の間のこと |
| 棗 (なつめ) | 薄茶を立てるための抹茶を入れておく容器 |
| 躙り口 (にじりぐち) | 茶室の出入り口 |
| 躙る (にじる) | 両手で体を支えて、膝で前進・後退する動きのこと |
| 半東 (はんとう) | 亭主(茶会や茶事の主催者)のサポート役の人 |
| 干菓子 (ひがし) | 落雁などの水分が少なく、日持ちするお菓子 |
| 縁高 (ふちだか) | 主菓子を入れておく容器 |
| 風炉 (ふろ) | 釜をかけておくための茶道具 |
| 風炉先屏風 (ふろさきびょうぶ) | 手前座に置いて使用する屏風のこと |
| 縁 (へり) | 畳の縁 |
| 松風 (まつかぜ) | 松の木の間を風が吹き抜ける時の音 |
| 末客 (まっきゃく) | 亭主から最も離れた席に座っている客人 |
| 水指 (みずさし) | 茶碗などを洗い清めるための水を入れておくための茶道具 |
| 水屋 (みずや) | 茶席の準備を行うための場所 |
| 水屋茶杓 (みずやちゃしゃく) | 茶入や棗に抹茶の粉末を移すために使用する茶杓 |
| 水屋壷 (みずやつぼ) | 水屋で使用する、水を溜めておくための壷 |
| 利休七則 (りきゅうしちそく) | 千利休が茶道の心得について表した七か条のこと |
| 炉 (ろ) | 湯を沸かすために火を起こし、釜をかけておく場所 |
| 炉開き (ろびらき) | 11月上旬ごろに炉を開け、釜を据えることで、茶道におけるお正月のようなもの |
| 炉縁 (ろぶち) | 11月~4月の炉の時期に、炉の周囲にはめる木枠のこと |
| 和敬清寂 (わけいせいじゃく) | 主客ともにお互いの心を和らげて敬い、茶室にある道具や茶会・茶事の雰囲気を清めるという意味 |
まとめ
茶道には、流派によって細かな違いはあるものの、さまざまな作法や言葉が存在します。
本記事を通じてそれらを知り、理解を深めることで、茶道初心者でも茶会や茶事を楽しむことができるでしょう。