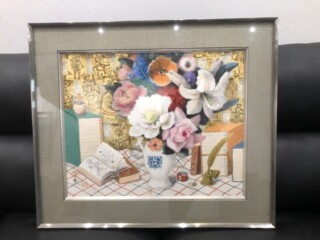児玉希望は大正から昭和にかけての日本画壇で大きな足跡を残した児玉希望は、広島県安芸高田市に生まれ、上京して川合玉堂に絵を学びました。1921年に画壇の登龍門であった帝国美術院展覧会に初入選、その後も入選を続け、1928年、1930年には最高賞である特選を受賞、帝展、新文展、日展という大舞台で存在感を示し、日本芸術院会員、日展評議員として東京画壇を牽引しました。生涯ひとつの画風に陥ることなく、常に新しい表現に挑み続けたため、その作品はひとりの画家によるものとは思えないほど多彩です。花鳥画や歴史画と範囲を広げ、戦後には、西洋絵画の摂取・融合を試みて色没骨法の実験を行うなど、晩年まであくなき探究を続けたことでも知られています。
緑和堂では、児玉希望の作品を強化買取中でございます。売却を検討されたい作品がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
堂本印象は1891年京都生れの日本画家です。本名三之助です。1910年京都市立美術工芸学校を卒業後、しばらく西陣織の図案描きに従事し、1918年、日本画家を志し て京都市立絵画専門学校に入学します。1919年に初出品した「深草」が第1回帝展に入選します。第3回展では「調鞠図」で特選、また、第6回展の「華厳」では帝国美術院賞を受賞するなど一躍画壇の花形となりました。絵画専門学校の教授として、また私塾東丘社の主宰者としても多くの後進を育成、1944年、帝室技芸員となりました。
戦後は、独自の社会風俗画により日本画壇に刺激を与えました。1955年以降は抽象表現の世界に分け入り、その華麗な変遷は世界を驚かせた。多くの国際展にも招かれ、1961年には文化勲章を受章しました。
緑和堂では、堂本印象の作品を強化買取中でございます。売却を検討されたい作品がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
上原古年は梶田半古および松本楓湖(ふうこ)の門人です。1877年、東京浅草に生まれの版画家、日本画家です。初め梶田半古に師事した後、松本楓湖に師事して日本画を学んでいます。岡倉覚三(天心)に招かれて5年間、日本美術院に勤務しました。日本絵画協会・日本美術院連合絵画共進会などに作品を出品しており、また、絵画審査員に嘱託として勤め、宮内省や外務省の用命を受け、作品を制作しています。
版画はやや寡作で、新版画に属する1928年制作に渡辺版画店から出版した木版画「道頓堀」のほか「春日の閑清」や「早春漁村」などといった穏やかな風景画及び美人画が見られます。1932年4月、渡辺版画店の主催によって行われた第三回現代創作木版画展覧会に「道頓堀(夜)」、「残灯」の2点の作品を出品しています。作風は穏やかな風景画が得意としています。
尾形月耕は、1859年9月に江戸京橋で生まれた浮世絵師・日本画家です。
絵を描き始めたのは父の勧めによるもので、1881年頃には新聞や雑誌の挿絵を手がけるようになり、人気を博しました。当時、日本の出版業界が勃興していたこともあり、新聞挿絵画家として絶大な支持を得ました。尾形月耕は、時代の風俗を的確に捉え、人々が求めるものを作品として発表できる画家でした。
また、師につかず独学で絵を習得し、挿絵や木版画を数多く手がけるなど、時代を代表する人気画家として高い画力を誇りました。特に人物画を得意とし、江戸や明治の風俗、美人画、故事・伝説など幅広い題材を描きました。その作風は、たおやかで繊細な花や美人から、力強い英雄まで多彩であり、多くの人々を魅了しました。
中村岳陵は、本名を中村恒吉といい、日本画家です。日本画に油絵の表現を取り入れた、独自の日本画のスタイルで注目された作家です。1890年、静岡県下田市に生まれた中村岳陵は、初期のゴーギャン、ルソーといった西洋の画家に影響を受けています。岳陵の画業は約70年に及ぶ長いものであり、その発表の場も前期の日本美術院展覧会から後期の日展へと、大きく舞台を移しています。戦後、横山大観との確執から日展に移ったと知られています。又その画題も、仏画や歴史画の伝統をふむもの、風俗画的性格のもの、更に花鳥や風景など、多岐にわたっています。しかし岳陵の作品においては、常にモチーフの細密な観察と写生が、重要な基盤となっています。
岩倉寿は香川県三豊郡山本町(現 三豊市山本町)出身の日本画家です。香川県立観音寺第一高等学校、京都市立美術大学(現 京都市立芸術大学)日本画科卒業。同大学専攻科修了します。京都市立芸術大学名誉教授です。京都市立美術大学在学中に日展への初入選を果たす。1959年(昭和34年)同大学卒業後、晨鳥社に入り、山口華楊に師事します。日展を中心に活躍する一方、大学に残り、後進の指導に当たってきました。1961年(昭和36年)同大学専攻科修了。1962年(昭和37年)同大学教授に就任。1972年(昭和47年)の第4回新日展では「柳図」が、続く1976年(昭和51年)の第8回新日展では「山里」が特選となります。日展評議員となった1990年(平成2年)には「晩夏」が日展内閣総理大臣賞を受賞、2003年(平成15年)は改組日展出品作「南の窓」が日本藝術院賞を受賞。岩倉寿の作品は写実を極め、風景や花鳥などの題材を伝統に根ざした淡い色調の現代的色彩表現で描きます。