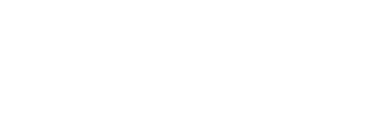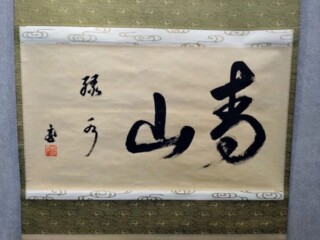川端近左は、江戸時代末期から200年ほど続く漆工芸師です。当代は六代目になります。
始まりは、京都で近江屋という油屋を営んでいた左兵衛(初代)の好きが高じて始めた蒔絵がいつしか家業になったとされ、近江屋の「近」と左兵衛の「左」を取って「近左」と名乗るようになったと言われています。二代以降も先代の意匠を継ぎつつ漆工芸の世界を広げ、多くの作品を残されています。
現在比較的よく見られるのは五代、六代の作品です。五代は日本画を学びながら四代に家業を師事していた人物で、五代襲名前に日展で数度入選するなど、確かな技術を持った方でした。六代は漆工芸家・冬木偉沙夫に師事し、工芸の基礎を固めました。その後五代に師事し、2000年に六代を襲名します。そして現在まで数多くの作品を制作されています。
川端近左の作品でも目を引くのは、やはり豪勢な蒔絵のあしらわれた棗などですが、そのほかにも盆や莨入、重箱、食籠など幅広く漆芸品を制作しており、質の高さからどれもが高く評価されています。
神山易久(こうやまやすひさ)は、信楽生まれ信楽育ちの信楽焼の陶芸家です。
1936年に生まれ、1955年より近江化学陶器で働きながら、陶磁器デザイナーの日根野作三に師事し、陶磁器の理解を深めました。
妻は同じく陶芸家の神山清子であり、同じ「近江化学陶器」という会社に勤めておりました。やがて「近江化学陶器」の経営が傾き始めたのを機に妻・清子が独立し、工房を立ち上げます。易久はライバル会社「日本陶飾」にヘッドハンティングされますが、人間関係の不和から四年で会社を辞め、清子の工房に入ります。
清子と共に半地上式穴窯「寸越窯」を築窯し、信楽陶器の製作、自然釉の再現を行いますが、その後離婚。以降は国内外で個展を開くなど広く活躍されました。
2019年には、二人がモデルとして採用されたNHKの連続テレビ小説『スカーレット』が放送されています。
神山清子の再現した自然釉は、窯の中で器に降りかかった蒔の灰が自然と釉薬状になる焼き方です。つまりは、釉薬を一切使わない焼き方と言えます。
あらかじめ釉薬を仕立てないので、窯の中での灰の掛かり方は自然の成り行きに任せる形となり、結果として様々な表情を見せるものとなります。清子と易久でもまた変わった表情の作品が制作されております。
尚美堂は、大阪淀屋橋にて1900年より続いている美術工芸品の製造・販売事業会社です。
初代となる江藤栄吉郎は、23歳の頃に大阪淀屋橋の南に「尚美堂」を開業しました。創業当初から美術工芸品の他、時計や貴金属など多角的な展開をしており、業界の発展に深く貢献してきました。
創業当時からオリジナル品として扱っているもので『純銀青海盆』があり、製造工程が機械化した今でも、最大の特徴である「青海波」は職人の手で打つなど、流通だけでなく自社製品へのこだわりも感じられます。純銀青海盆をはじめ銀製品を多く制作しており、銀瓶などは今なお高い人気を持っています。
近年では宝飾品のメンテナンスや贈答品の製造・販売にも力を入れるなど、紡いできた伝統をもとにさらに枝葉を広げております。
いいものだけを愛したい、いいものだけをお勧めしたい、という尚美堂の心は伝統の中で今も育まれており、多くの人に支持を得ています。
美術品・骨董品として尚美堂作品は高い評価を得ているお品物が多いです。
レンブラント・ファン・レイン(Rembrandt Harmenszoon van Rijn)はオランダの画家です。
バロック期に活躍し、フェルメールなどと並べて語られることが多く、時代を代表する画家です。バロック様式の絵画は強い明暗法と、リアリズム的でありながら躍動感のある構図が特徴的です。
レンブラントはその中でも「光と影の魔術師」と呼びならわされるほど、卓越した明暗表現を操る画家として知られています。
生涯に渡って絵画と向き合い、描き続けた彼ですが、その裏では度重なる不幸がありました。
20代で画家としての名声を得、結婚。妻・サスキアとの間に四人の子をもうけますが、そのうち三人が間もなく死去。のちの大傑作となる絵画『夜警』の制作中に妻サスキアまでが結核で死去してしまいます。その後は財政困難に陥り、借金に追われながら晩年期を過ごすなど、まさに激動の生涯でした。
晩年にあってもレンブラントは筆を離さず、その人生を落とし込むように絵画を描き続けました。主には油彩。そして銅版画や、1000を超えるほどのデッサンなど、名実ともに大作家として西洋美術史に名を刻んでいます。
中国文人の文房趣味とされる硯、墨、筆、紙の四つの文房具のことを文房四宝(ぶんぼうしほう)といい、文房四宝の硯の中でも最高峰とされているのが今回ご紹介する端渓硯になります。
中国の硯は唐硯(とうけん)と呼ばれ中国四大名硯として種類は端渓硯(たんけいけん)、歙州硯(きゅうじゅうけん)、洮河緑石硯(とうがりょくせきけん)澄泥硯(ちょうでいけん)の大きく4つに分けられます。
この他にも代表的なもので松花江緑石硯(しょうかこうりょくせきけん)、羅紋硯(らもんけん)があります。
唐硯全体の特徴としては装飾が豪華なものが多いという点と、硯に天然石が持つ紋様が表れるという点にあります。
この紋様のことを石紋(せきもん)といい、天然石特有の多種多様な紋様が、観賞価値を高めるためには非常に重要なものとなっております。
石紋で有名なものが、青花(せいか)、蕉葉白(しょうようはく)、冰紋(ひょうもん)臙脂暈(えんじうん)翡翠(ひすい)石眼(せきがん)金、銀線(きん、ぎんせん)等多くの種類が存在します。
画像の物は硯全体が壷型の形をしており、二体の獅子が彫刻された珍しいお品物であり、機械で彫刻されたものではなく手掘りの作品で、こちらが老坑と呼ばれる珍しい石を使っていたり石の紋様である石紋というものがあれば高値の評価額が期待できるお品物になっております。
この他にも、中国骨董は中国人バイヤーの方にも大変人気があり、中国で起きた文化大革命(1966年~1977年)以前のお品物でしたら、書道具に限らず高値の評価額が期待できます。
吉田萩苑は1940年 山口県萩市三見床並に生まれます。15歳より人間国宝の十代 三輪休雪に入門し修行を重ね、天鵬山窯の開設に際し技術指導者として招かれ尽力しました。
1968年生まれ故郷である山口県萩市玉江に玉隆窯を開設しますが1986年の事故により46歳という若さでこの世を去りました。
吉田萩苑に関する略歴や詳しい情報はかなり少なく、現状分かっているのは上記の部分のみとなります。